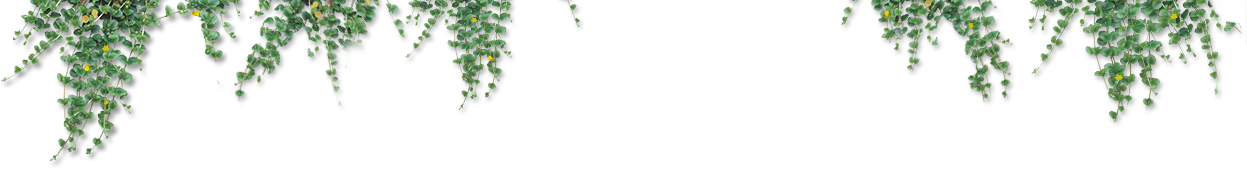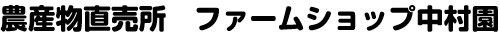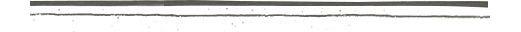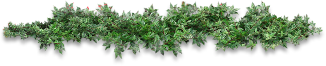
インフォメーション
2025-11-30 20:30:00
今日の売り場
今日の売り場です。
上段・・・むかご、八つ頭、春菊、八つ子、サニーレタス、ラディッシュ、ルッコラ、水菜
中段・・・キウイフルーツ(アップル、東京ゴールド)、サトイモ、ほうれん草、小松菜、ニンジン、大根
下段・・・ターサイ、長芋、ネギ、かぶ、ブロッコリー、キャベツ、聖護院大根、赤かぶ
反対側・・・白菜、サツマイモ(べにはるか、シルクスイート、栗かぐや)、ゴボウ、ニンジン
30種類近いものが並ぶようになりました。まさに直売シーズンです。
花小金井駅近くと、東久留米市前沢で、スーパーマーケットの改装・新装オープンが相次いでいます。
その開店セールの影響でしょうが少し客足が伸び悩んでいます。
一過性のものだと思うので、あまり気にしないようにはしていますが、このところの物価高の影響か、こういう安売りセールには飛びつくお客さんも多いのかなと思います。
あからさまにお宅は高いと言われることもありますが、安売りが目的ではないと思っていますので、あしからずご了承くださいとしか言えません。
農家の庭先直売所としてできることをやっていくしかないと思っています。できることはやっているつもりです。あとはお客さんのご評価ということで。
2025-11-30 20:22:00
長芋・むかごを収穫しました
長芋の収穫を始めました。
一昨日、ボランティアさんにむかごを拾ってもらいましたので、ようやく長芋も収穫できるようになりました。
今年の長芋は、やや細いように思います。そして、長いです。
収穫は結構大変でした。ぶっといのが取れると良いのですが、今年はそうもいかないようです。
夏の暑さが続き、茎葉の枯れるのが遅くなっているようにも思います。10年前よりは半月以上は遅い収穫かもしれません。
長芋も、収穫したての新鮮なものは格別です。ぜひご利用ください。
2025-11-28 20:00:00
東京都庁・東京都農林水産振興財団への意見具申
東京都庁農林水産部長、東京都農林水産振興財団理事長、東京都農林総合研究センター所長に対して、意見具申を行いました。
詳細は以下のPDF文書をご覧ください。
![]() 知的財産担当者の人事異動について1.pdf (0.54MB)
知的財産担当者の人事異動について1.pdf (0.54MB)
2025-11-17 00:03:00
「地産地消イレブン」に賛同します
先日参加した全国農林水産物直売サミットで、主催者の都市農山漁村交流活性化機構の方から「地産地消イレブン」のご紹介がありました。
機構で推進している地産地消の理念を11にまとめたもので、非常によくできていると思いました。
交流会の帰りがけ(新幹線の時間のため、お開き前に中座しました)に、のぼり旗が受付台にご自由にお持ちくださいと積んであったたので、いただいてまいりました。
昨日より、当園店頭に掲示しています。
地産地消イレブンは、以下の11か条です。
1 作り手から届く小さなメッセージを大切にしよう
2 健康で豊かな暮らしをつくろう
3 小さい価値を大切にしよう
4 環境負荷を軽くしよう
5 食料システムの最前線として考えよう
6 新たな食料課題にも対応しよう
7 ローカルの魅力を発見しよう
8 どの地域でも進めよう
9 リアルな体験から生きる実感を得よう
10 活動を見える化しよう
11 地産地消で日本を変えよう
地産地消の理念を短く、しかも網羅してあり、私たちが常に念頭に置くべきと思いました。しばらくの間、当園店頭に掲げます。
旗の下にチラシをコピーを掲示しますので、ご覧いただければと思います。
https://www.kouryu.or.jp/events_seminar/chisanchisho11.html
なお別件ですが、現在小平市で行われている「農産物直売所デジタルスタンプラリー」について、お問い合わせいただくこともありますが、
当園はスタンプラリーの対象にはなっていません。あしからずご了承ください。
2025-11-16 23:57:00
赤かぶ収穫しています
赤かぶの収穫が始まりました。
今年はタネの入手難で、昨年まで作付けていた品種(愛真紅3号)ではなく、別の品種(恵星紅)を作付けています。
違いは、やや赤みが薄いような気がしますが、漬けたときの出来上がりはほぼ同じだと思います。
かぶの果肉は白で、漬けたときに皮の部分の赤い色素が染みて、全体が赤くなります。
甘酢で漬けるのが一般的です(塩で漬けてから甘酢で漬けるやり方が丁寧なやり方です)。
お正月の料理に出されることが多いかもしれませんが、お正月ではなくても食べていいと思います。
ぜひご利用ください。
※「ビーツ」ではありません。