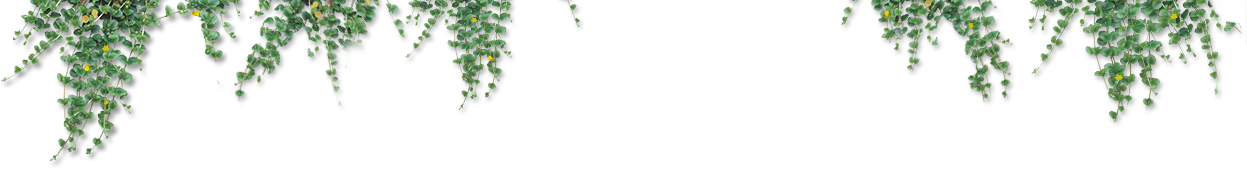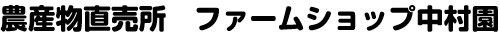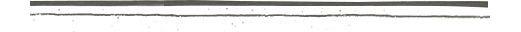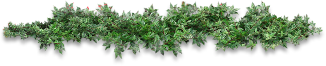
インフォメーション
2026-02-02 22:48:00
資産管理の研修会
資産管理部会長の業務として、東京都JA資産管理部会連絡協議会の研修会が開催され、出席してまいりました。
内容は、リノベーションに関することと、本年度の税制改正に関することでした。
アパートのリノベーションは、家賃の値上げを試みる時期に有効な手段となるようです。
家賃の安さだけにとらわれない入居者が多くおられるようです。
資産管理部会では、2月にも本部会での研修が予定されています。
2026-01-31 22:43:00
関東東海花展を見学しました
1月30日、東京カジュアルフラワー研究会の定例会として、池袋サンシャインシティで行われている関東東海花の展覧会を見学しました。
今年は栃木県の担当だそうですが、来年が東京都の当番になるそうで農総研や普及センターの職員もたくさんおられました。
関東東海11都県が参加していますが、県により得意分野があるようで、東京の場合は花苗が多く、直売切り花で参考になるものは埼玉県などが多かったです。
ユリについては、オリエンタル系で非常に大輪になるものや、八重のものが上位になっていました。
私のところで栽培して、売れるかを考えると、ちょっと・・・となりますが、非常に品質の良いものでした。
カジュアルフラワー研究会の会員で出品している人はいませんが、東京切り花倶楽部の方がラナンキュラスを出されていて、入賞されていました。
見学後は、池袋の居酒屋でカジュアルフラワー研究会の新年会を開催し、懇親を深めてまいりました。
カジュアルフラワー研究会も、意欲的な新会員を入れ、活動を活発化させていきたいと考えおります。
2026-01-03 22:15:00
あけましておめでとうございます
令和8年2026年あけましておめでとうございます。
本年は箱根駅伝に農大が出場したので、2日間応援に行ってまいりました。
箱根駅伝が終わらないと、私にはお正月が来た感じがしません。明日はようやくゆっくりできます。
学生さんたちの真剣勝負を間近に接し、すがすがしい気持ちです。タイムや順位などは気になりませんし、どこが優勝したかも関係ありません。そんな気持ちで駅伝応援をしてきました。
「勉強する農家」を旗印に、庭先直売所の仕事をしています。最近は、「モノ言う農家」にもなってきたのかもしれません。
アイツはうるさいやつだと思われたいわけではないので、ここぞというときにモノ言えるようになりたいと思います。
引き続き、勉強する農家ではありたいと思います。本棚の積読を少しずつでも解消したいと思います。
昨年は山形県に行ってきました。鶴岡市は魅力的な食の街だと思いました。産直あぐりの客入りにも驚きました。
冬にも行ってみたいですね。行けるかな。
今年は八戸市の舘鼻岸壁朝市に行ってみたいと思っています。
直売所の在り方、農業のやり方に大きな変化があるわけではありませんが、何の変化もないわけでもありません。
少しずつ改善をしながら、求められるものを作りたいと思っています。
今年は、近隣で大きな開発工事が始まります。
当園にとって、決して利益になることではないのですが、仕方がありません。
道路工事などでお客様にもご不便をおかけすることもあるかもしれません。
当園としては、今後とも、この地で農業を続けていくことができるよう、真摯に努力を積み重ねてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2025-12-31 14:00:00
年内の販売はすべて終了いたしました
年内の販売はすべて終了いたしました。本年もたくさんのご来園・ご購入ありがとうございました。
年始は、しばらくの期間休業いたします。例年1週間~10日程度お休みをいただいています。再開の際にはまたこちらで告知させていただきます。
皆様には良き新年をお迎えください。
なお1月2日・3日は箱根駅伝が開催されます。
東京農業大学校友会東京都支部の活動として、2年前と同様に、馬場先門付近での応援活動を予定しております。
在学生・卒業生の方、また東京農業大学を応援していただける方であればどなたでも、スタート・ゴールの約1時間前にお集まりください。
テレビ観戦の方も多いかと思いますが、馬場先門付近にご注目頂ければ幸いです。
2025-12-29 00:00:00
農業視察・技術的相談についてのおことわり
★★★2021・1・22追記★★★
本稿は2020年12月7日に書きました。しばらくの期間、トップに来るように日付を変えて表示させます。
★★★★★★
テレビに出していただいたり、またこのようなホームページをしている関係で、当園のようなところにも視察に来たいという依頼が来ることがあります。
私自身も数多くの所属団体の事業を通じて、多くの農家・圃場の視察をさせていただき、学ばせていただいてきました。
当然、そのような団体からのご依頼にはお応えすべきものと思っております。視察を受け入れることが、受け入れる側にとっても勉強になるとも思っています。
お世話になっている所属団体や、農業改良普及センター・農協・市役所などを通じてご紹介・ご依頼があった視察は、これまでもすべて受け入れてまいりました。
しかしながら、あくまでもこれは事前にご紹介・ご依頼があったものです。
このところ、事前の連絡がなく、いきなり当園を見学したいと来訪されることが、複数件ありました。
当方も常に暇にしているわけではありませんので、十分な対応ができるものでもありません。
まして、名刺の1枚も差し出さないで、来訪者の方がどのような方でどこで何をされているのかも分からない状態で、〇〇について教えてほしいと言われても、何も話しようがありません。
とりわけ、農業者ではない、家庭園芸を楽しまれている方の場合は、当方とは立場が違うことをご理解ください。
当園への視察については、まずはご自身がお住まいの地域の農業改良普及センターまたは農協にご相談してください。
そちらの普及員さんまたは農協の指導員さんに、当方を担当する普及員さんと話をしていただき、普及員さん同士で視察の計画を立てていただければ当方としては100%お応えいたします。
家庭園芸を楽しまれている方には、視察をお受けする用意はありませんので、ご理解ください。
★★★2021.1.23追記★★★
関連しますが、電話・メールでのお問い合わせについても、ご配慮をお願いいたします。
原則として、農業技術に関する相談については、応じません。応じられません。
先日電話で、ホームページを見たといってキウイフルーツの剪定のやり方を聞かれた方がおられましたが、答えられるわけがありません。
当方が、先方様の畑を見たわけでもありませんし、仮に見ていたとしても、電話で話ができるような(口で説明できるような)事柄でないことは、農家であればお判りになることでしょう。
果樹の剪定は、畑の状態、樹の状態、枝の状態をそれぞれ見極めながら、販売状況など経営判断も含め、一つ一つを整えていくものであり、電話でやり方が説明できるようなものではありません。少なくとも、私自身はそこまでレベルは低くありません。
地域の普及員さんや農協さんなどに指導を仰ぎながら、地域の生産者仲間とともに、技術を習得していくべきものであると考えております。
そもそも、どちらのどなた様かもお聞きしておりませんでしたが、まずはこういったところから改善していただければと存じます。
★★★2023.04.30追記★★★
大学生の卒業論文などでの視察・見学・ヒアリングなどのご依頼は、直接のご連絡をいただければお受けします(平均して、年に1~2件程度ご依頼があります)。
事前に、所属大学・学科・専門分野・ご指導の先生のお名前・卒論の計画概要を、メールでご連絡いただければと思います(お問い合わせ欄からご連絡ください)。
なお、卒論完成後に概要・要旨などでも構いませんので、どのような論文を書かれたのかご報告いただくことを条件にさせていただいております。
当方の繁忙期(特に年末)についてはお受けできないことをご理解ください。また、当ホームページの内容を出来る限りたくさん読んでからお越しください。圃場見学・ヒアリング含め、1~2時間程度になります。
これまで当園に来られた学生さんは、記憶がある限りで、武蔵野美術大(建築)、法政大(生命科学)、国士館大(地理)、東洋英和女子大(保育)、東京農大(バイオビジネス・2名)、東大大学院(都市計画)、東洋大大学院(国際地域学・留学生)、千葉大(緑地環境学)、東京学芸大(環境教育)、早稲田大(地理)などです。
また東京学芸大(民俗学)、岐阜大(地理)、東大(都市計画)、千葉大(緑地環境学)、東京農工大(昆虫生化学)の先生も来られました。
学生さん、先生方に研究していただくことで、都市農業に少しでプラスとなればと思い、原則すべてお引き受けしています。私自身も勉強させていただきます。是非、研究成果を都市農業に還元していただきたいと思います。
小・中学生、普通科の高校生の見学(夏休みの宿題へのご協力等)については、かみ砕いての説明をするのが不得手ですので、原則としてお断りすることにしています。消費者・飲食業者等の方の圃場見学についても、市役所・観光協会などの特別の依頼があるものを除き、原則ご遠慮いただいています。