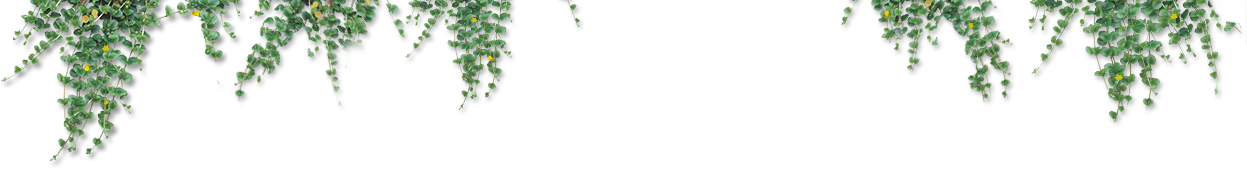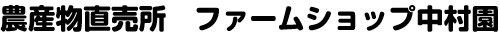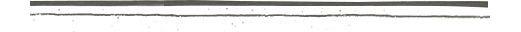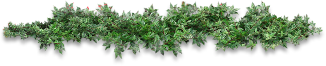
インフォメーション
2022-11-08 22:07:00
キウイフルーツの販売を始めました
昨日よりキウイフルーツの販売を始めました。
品種は、東京ゴールドとアップルキウイです。
たくさんありますので、是非ご利用ください。
直売所
上段・・・むかご、ルッコラ、ラディッシュ、ズイキ、サニーレタス、ターサイ
中段・・・かぶ、ごぼう、さといも、小松菜、ブロッコリー、にんじん、だいこん
下段・・・サツマイモ、キウイ(東京ゴールド、アップルキウイ)、水菜、にんじん、ユリ(切り花)
2022-11-05 23:28:00
農研機構 ゲノム編集施設見学会に参加しました
10月25日に、つくば市の農研機構で行われた、ゲノム編集施設見学会に参加してきました。
ゲノム編集技術を使った品種改良の現場を見てまいりました。
現在、農研機構で行われているのは、ジャガイモと小麦での育種のようです。
ジャガイモでは、栽培上問題となる緑化(ソラニン、チャコニンという毒素が生成される)を防ぐ品種改良です。
小麦では、やはり栽培上問題となる穂発芽を抑制する品種改良です。
いずれも興味深く見てまいりました。
たくさんの写真を撮ってきたのですが、このサイトで多数の写真を公開するのは適当ではないため、PDFの文書を作成いたしました。
よろしければご覧ください。
![]() 農研機構 ゲノム編集施設見学会20221025pdf.pdf (3.87MB)
農研機構 ゲノム編集施設見学会20221025pdf.pdf (3.87MB)
#ゲノム編集
#毒素
#ジャガイモ
#穂発芽
#小麦
2022-10-30 17:26:00
近隣の工事について
現在、当園の東隣で工事が行われています。
某社の集配センター兼事務所が出来ると聞いております。
10月31日と11月1日に、道路の切り下げ工事が行われると聞いております。
東京街道が一時、片側通行になるものと思いますが、当園については平常営業いたします。
車でお越しの方は、ご遠慮なく、当園内に駐車されますよう、お願いいたします。
2022-10-30 17:24:00
80万PVに達しました
本日午前中、当ホームページは80万PV(ページビュー)を超えました。
ご覧いただき、ありがとうございます。
ホームページ開設 2014.8.14
10万PV 2017.5.1
20万PV 2018.10.8
30万PV 2019.9.29
40万PV 2020.7.17
50万PV 2021・1・29
60万PV 2021・10・7
70万PV 2022・04・19
80万PV 2022・10・30